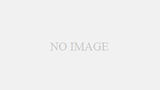はじめに
日本のお米は、生産者(農家)→集荷・出荷(農協・JAなど)→卸売業者(米卸)→小売業者(スーパー・米店・ネットショップなど)→消費者という流れが一般的だと思います。最近、スーパーなど店頭で5キロ5,000円で販売されていましたが、実際農家さんはいくらで農協・JAなどに買ってもらっているのでしょうか?また、どうして農協・JAを通さなくてはいけないのでしょうか?個人的に考えてみました。
各役割
- 生産者(農家)は、水田で稲作を行い収穫後に籾(もみ)から玄米(脱穀作業)にする作業を行って農協・JAに卸します。
- 農協・JAなどは、地域の農家からお米を集荷し、共同で保管・管理・品質検査などを行い卸売業者や小売店へ出荷します。
- 卸売業者は、JAや農家から買い取ったお米を保管、精米、ブレンドなどして、小売業者や外食産業に供給。品質や等級別に仕分けされて価格が決まる。
- 小売業者(スーパー・米店・ネットショップなど)は消費者(エンドユーザー)に販売。
- 消費者はスーパーなどでお米を買って最終的に家庭で炊飯され食卓へ。
流通の特徴と課題
この流れによって、生産地・農家・精米日などの情報が追える体制が整備されて、価格変動が起きにくい安定した供給が実現される。しかし、近年の若者の米離れ、パンやパスタ・麺類などの多様化による需要の減少や、農家によるネット販売・直売所での販売が拡大、またブランド米の価格高騰や、インバウンド需要や海外での日本食ブームなどによって流通システムに異変がおきてるのでは?
2024年のJAの生産者からの買取価格は60kgで16,800円、5kgで1,400円相当です。店頭販売価格は5kgで3,500円~4,000円だったみたいです。
政府の備蓄米放出が2025年3月に行われたが入札価格は5kg当たりで1,700円だそうです。今の流通に乗せると店頭価格は3,500円程度になるそうですが、3か月経ったいまだに一部の地域で少量しか流通していないようです。小泉大臣によって随意契約による備蓄米の放出が5月末から行われてますが、流出価格は5kgで900円、店頭販売価格で1,700円~2,100円で1週間程度で全国の店頭に出始めています。
※玄米から精米する期間や袋詰めラベル張り運搬時間はもちろん、それにかかる費用も「入札」も「随意契約」も同じくかかります。備蓄年度による多少の価格差はあります。
考察
- 農家さんは農協やJAに買ってもらわないといけないのか?
- 流通段階で卸業者が流通量を操作して価格を吊り上げてはいないか?
- 消費者は精米でないといけないのか?→玄米でもいいのでは・・・
自分なりの回答
米農家さんは、お米を作るのにトラクターや田植え機、コンバイン、籾(もみ)摺り機に乾燥機や肥料・苗代などかなりの出費が必要です。その資金援助に農協やJAが一役買ってるのではないか?また、流通においては実際どれくらいのお米が卸業者の倉庫に眠っているのか分からないです。需要が増えて供給が減れば価格が高騰します。考えたくはないですが、卸業者が出し惜しみをして価格を吊り上げてるかもしれません。最後に私的には安ければ玄米でもよくないかと思います、道端にコイン精米機をよく見かけますが、20kg精米するのに約5分間、400円ぐらいかかりますがあまり苦になりません。
まとめ
米の生産量が減った今、一部の業者が独占してる米の流通システムに問題があると思います。それは、米の流通に時間がかかるのと、卸業者が流通量を操作して価格を操作できるからです。生産者は個人から法人化して小規模から大規模な農業へと転換していき、農協やJAに頼らなくてもSNSや独自の流通ルートを作れば米を高く売ることができ、消費者へも安く提供出来るのではないでしょうか?